
|
|
小説 春の路この小説は 海の華の続編である 冬の華の続編である 春の華の続編である 夏の華の続編である 秋の華の続編である 冬の路の続編である この作品は省三33歳からの軌道です。ご興味が御座いましたら華シリーズもお読み頂けましたらうれしゅう御座います・・・お幸せに。  春の路 陽炎浮き立ち人の心を迷わすか、だから手を携えて・・・。 春の路 1  最初のうちは水、金、土曜日に、迎えの車が店先について待っていた。水島の科学会社に勤めている佳世ちゃんが、会社を終わって来てくれたのだった。 省三にはその車に乗るのが勇気の居ることであった。ポケットの中に発作のときに飲む薬を忍ばせなくてはならなかった。車の閉塞感が発作を齎す要因の一つになっていた。 「宜しくお願いいたします」 育子は佳世に明るく言った。 「はい」 と、佳世は頷いた。 省三は助手席に乗って緊張した。不安が常に押し寄せ、前を見るのも怖かった。もう目を瞑るしかないかと開き直るしかなかった。開き直ると意外と楽になった。 佳世ちゃんは何も言わずに前を見て運転していた。ラジオから英会話の放送 が流れていた。まだ運転免許を取って間もないことを知らなかった。 倉敷の中央公民館までの廿分間は不安とそれをなだめる心の葛藤だった。 「ありがとう」 佳世に導かれて部屋に入ると戸倉が近寄り言った。ジャケットをラフに着こなしていた。 「なにも出来ないけれど・・・」 省三はそう言って、部屋の中を見た。四五人の青年が軽い体操をしていた。 「お早う御座います」の言葉が幾つも飛んできた。 省三は軽く頭を下げた。 「そこらへんに座って・・・この人が今村省三さん・・・これからきてくださる事になった。分らんことがあったら何でも聞いて・・・」 戸倉がみんなに言った。 「宜しくお願いいたします」 「こちらこそ・・・」 省三は頭を下げた。 一人ひとりの紹介があったが、省三は頭を下げて受けボーとして見ていた。 男が二人で女が四人いた。それぞれ名前を聞いたが顔と一致するのは何時になるだろうかと思った。 「始めようか」 戸倉が言った。 「宜しくお願いいたします」といってみんなが出て行った。どこへ行ったのだろうかと省三は思った。後で分ったことだが、公民館の前にある名刹観竜寺の石段を走りに行ったとのことだった。百段くらいを翔りあがり、何回か繰り返し、余裕のある人はうさぎ跳びで上がり下がりをするとのことだった。 ハアハアと息が上がっているときに発声練習をした。息が上がっていないと幾ら練習しても駄目なのだった。そのあとは柔軟体操をして終わった。 省三が前に来ていた時には石段の駆け上がりはなかっただけに青年たちの心意気を感じた。 「この秋に公演する台本の回し読みする」 戸倉は誰に言うともなしに言ったが、省三に言ったのだった。 練習場の戸倉は極端に愛想がなくなる癖があった。 省三は回し読みを聞いていた。不思議なことに不安発作は起きずリラックスをしてその場にいることができた。 ―この分では大丈夫かーと省三は安堵した。 初日はそのように終わった。 佳世ちゃんの運転する車で帰途についた。車の中には相変わらず英語のレッスンが流れていた。 「ご苦労様でした」 佳世は緊張した顔で言った。 育子が心配そうな顔で出てきて、 「お世話になりました」 と、佳世に声を掛けた。テールランプが見えなくなるまで見送っていた。 「どうだった」 「何もなくてよかった」 「そう」 「ああ」 省三は喉が乾いていることに気づき、コップいっぱいを一息に飲み干した。 今日の回し読みを聞いていて、鼻濁が出来ていないこと、そして脚本の分析に問題があることに気づいたのだった。 気が張っていたのか自室に入るとほっとした。久しぶりの緊張を快く感じていた。 国立競技場を胸を張って行進する岡山選手団がいた。薄い黄色のユニホームを着ての行進が続いていた。省三は銀傘の下でカメラのシッターを切りまくっていた。人生に何度もない華舞台に彼らは上がっていたのだ。彼らの顔はきらきらと輝き自信に満ちているように見えた。やることはやったという自負なのかと思った。 常盤の宮が開会の挨拶を、中曽根総理が祝辞を述べた。式典は最高潮に達していた。 机の前に座って直ぐ転寝をしたらしい、そんな夢を見た。 戸倉が来てくれということはふたたび青年大会を目指すということなのかと思った。 国体、インターハイ、青年大会と三大イベントがあるが・・・。省三は国体やインターハイには何の興味もなかった。青年大会は勤労者の大会だった。仕事をしてその余暇に文化に接し、スポーツを鍛錬研鑽してその技量を競う大会であった。県の青年大会で最優秀賞を取らなくてはその権利はもらえないのだ。エリートでないのが省三の心を煽っていた。 今日のメンバーでそこまで行けるか・・・。心意気は買いたいが・・・。それだけでは駄目だ・・・。一人ひとりの人間としての資質を高めなくてはならないと考えた。 今日初めて練習場へ行きこのように感じることはやはり好きなのだと思った。 育子は省三の性格を掴んでいたのだった。 省三は書きたい衝動がふつふつと湧き上がるのを感じていた。 県の青年大会は秋、後一年あるが、その前に演劇の苦しさと喜びを感じ取らさなくてはならないと思った。 今日の回し読みの演劇はメンバーの力量を超えているものであった。観客は二人か・・・でも観客の数ではない・・・その公演を終えた後、かかわった青年がどれだけ進歩しているかなのだ。感動したかなのだ。一つ大きな演劇を公演させ自信を持たせ感動の共有をしなくては無理だと考えた。 書きたいものを頭の中で探した。この何年も最後まで書いたものはなかった。書き出しても途中で投げ出しているものばかりだった。 その時階段を上がってくる小さな足音がした。 「おとん、ご飯じゃ」 悠一がドアを開け声を掛けた。悠一の後ろには豊太がついてきていた。 「ああ、ありがとう・・・気をつけて下りろよ」 省三は振り返って声を掛けた。 「ああ」「うん」 と二人は返事をして下りていった。 その顔を見て胸が熱くなった。 そうか、あの青年達を子供にして舞台を走りまわしてはと思った。これもなにかの啓示かと考えた。いつもなら育子が夕餉を伝えてきていたのだった。今日に限って二人の子供が・・・それをなにかの定めと位置づける弱い心が省三にあったのだった。迷いの中に居るとき人はそんな思いに取り付かれるものだった。 書く気になっている自分に省三は驚いていた。 その夜、久しぶりに梅木女史から電話があった。今までにも思い出したように梅木女子からは電話がかかってきていた。 主人の転勤で筑波へ転居していた。そのことは前の電話で伝えてきていた。 「元気、その後どうなの」 受話器の中から綺麗な声が聞こえてきていた。その声に惚れた杉村春子が文学座へ入ることを進めたということだった。彼女の父親は人間魚雷回転の設計に携わり戦後C級戦犯の汚名を着せられ、人の噂により家族は住居も定まらず転々としたということだった。平凡な路を選び結婚し子供を二人産んでいた。彼女は専業主婦の時間を無駄には過ごさなかった。童話教室に通い市民童話賞を取り、大人の小説に挑戦し女流文学賞をものにしていた。 「ままあまあです」 省三は元気なく応えた。 「そう、今は冬かもしれんね・・・。だけど春はきっと来るは・・・」 「なにか・・・」 「そうそう、私が帰られたらいいのだけれど、ある人に逢って欲しいの・・・。私の分野ではないし・・・これは今村さんにお願いしょうかと・・・。この前に私のところに本が贈られてきたのよ。『己なき日々』という表題だけど、戦前戦中戦後の女教師の生き様を書いたものなの・・・読後を書いて送ったのだけど・・・。逢いたいということなので・・・。でも今は手が離せないのよ・・・。急ぎの原稿もあるし、子供の大学進学があって・・・それで・・・」 「ああ、いいですよ。僕でよかったら・・・」 「身体が心配で・・・こんなこと頼んでいいのかなって・・・」 「妻に付き添ってもらっても行きますから・・・」 「そう、有難いわ・・・困ったときは今村さんね・・・」 それから小説のことや踊りのこと、子供達の事に話は及んで花が咲いた。延々三時間の会話が続いたのだった。 昔、梅木女史が岡山に居た頃は夜の十一時に電話かかり朝の六時まで、梅木女子が受話器の向こうで原稿を読むのを聞かされたことを思い出していた。そんなときが週に何度もあったのだった。その頃省三は何時電話がかかってきてもいいように何もかも済ませて待ちの体勢になっていたのだった。 「終わったの」 と育子は冷えた夕餉を温めて上がってきたのは次の日になっていた。梅木女子から電話がかかってきたら長いということを知っていたので頃あいをみはらかって持って来たのだった。電話は少し前に終わり一瞬ボーとしていた時だった。省三は梅木女史の依頼を伝えた。 「お元気なのね。何よりだね・・・。それでどうするつりなの」 「断れなかった」 「でしょうね」 「連絡して、逢おうと思っている」 「そうね」 「一緒に行ってくれるか」 「いいわ」 省三の永い一日はそうして終わった。が、なかなか寝付けなかった。 2  二人の子供が通う保育園の坂には桜が満開になっていた。園長の旦那さんがお寺の住職をし、園の理事長を兼ねていた。園の裏にお寺があってなだらかな坂道が続きその道沿いに櫻の老木があり春を告げていたのだった。 園の遠足はその花見だった。 育子と二人で参加していた。カメラを胸からぶら提げて子供達の表情を追った。しだれ櫻を見上げながらその花びらがすべてお日様を仰いではいないことに気がついた。人間もそうかと省三は思った。 櫻並木が続き・・・。この光景を何かで読んだ記憶があると・・・。風もなく静かに桜並木が続き・・・その中に人間が居たら・・・。 「あ・・・」 と省三は声を上げた。 坂口安吾の「満開の櫻の木の下で」を思い出したのだった。 事故以来鮮明に何かが脳裏に去来することがなかっただけに驚いた。 「おとん」 悠一が省三の袖を引っ張っているのも忘れていた。目の前にわが子の顔が迫っていた。 「どうした」 省三は優しく問った。悠一は小さな指を指した。そこには園長が笑いながら立っていた。 「夜はこの下を通るのが怖くて・・・」 園長は櫻を見上げながら言った。 櫻の命を感じながら歩くことは恐ろしいことだろうと思った。 「本当に良かったわ。あれから子供達の表情が違ってきましたの」 園長は満面笑みで育子に声を掛けた。 「それは宜しゅう御座いました」 育子が頭を下げながらそれに応じた。 秋の頃の武本が描いた壁絵のことを言っているのだった。 あの頃から省三は少しずつ変わってきていたのだった。 何かを目的にして外にでなくてはだめだったのだと思った。 戸倉の所へは週に三回行って、ただ黙って座って見詰めていた。戸倉は何も言わなかった。それが約束だといわんばかりだった。 先日、梅木女子から連絡があり「己なき日々」を書いた佐竹が倉敷に来てくれるということで明後日会う事になっていた。省三の症状を言ったら出向くという事になったのだった。 省三は倉敷駅に近い旅館に席を取っていた。梅木女史からは何をどうということは一切なかった。佐竹からなにかの提言があるのだろうと思った。 山を背にした校舎の前で住人足らずの子供たちが写っていた。その中央に白いブラウスを着てお下げに垂らした若い日の佐竹がいた。セピア色が年月の流れを現していた。 駅前の旅館で佐竹に会った。時間より早く行ったのだが佐竹のほうが早く来ていた。佐竹は座卓を退いて丁寧に礼を言ったのだった。省三と育子は体を小さくしてそれに応えた。 「私が最初に赴任しました小学校の分教場で写したものです」と出されたのがその写真だった。白いフラウスといえば女子師範の制服だった。 「十八のまだ何も知らない女性でした・・・」 省三は佐竹を主人公にした台本の冒頭はこのように書いている・・・。 佐武 私は、今年の四月一日をもちまして、四十五年の教員生活 を無事に終えることが出来ました。振り返り見れば、多くのこと が、今にして思えば、ああもすれば良かった、こうもすれば良か った・・・。色々のそのときそのときの出来事が後悔となって思 いかえされます。走馬灯のように頭の隅を掠めます。楽しい事も ありました。嬉しいことも・・・ですが辛い悲しいことのほうが ・・・。 あれは・・・{遠くにまなざしを投げて}私が女子師範を終え まして、国民学校に奉職いたしましたのは、大東亜戦争たけなわ の昭和十八年の春でございました。私の故郷からおよそ八里の山 奥の小さな国民学校でした。 その年は春の来るのが遅く、教室の窓からも、運動場からも、 目の前に雪を残した蒜山三座の山肌が、柔らかな日差しを受けて きらきらと輝き、眩しいくらいに跳ね返しておりました。校庭の したを流れる小川の細流は雪解け水を集めて勢いよく流れ、岩に 砕けて白い飛沫を上げておりました。 その国民学校には、一年生から六年生まで十五名、どの子も、 父を兄を戦地に送り出している家の子供達でしたが、みんな明る い子供達で、きらきらと輝く瞳を持っておりました。 佐竹は写真を出し、手紙を出して説明をした。眼差し派遠く彼方へ向いていたがそれ定まっていなかった。  佐武 私に大きな問題が持ち上がりましたのは、昭和十九年の冬 も終わりの頃でございました。 戦局は、昭和十八年の春を境にして敗戦色も濃くなり、小学生 以上の生徒は勤労学徒動員であらゆる軍需工場へ出掛け、学業ど ころではありませんでした。また、学徒出陣令により、大学生は 学業半ばで予備役として入隊、と、戦火の中へと巻き込まれてい きました。兵役も五十歳に引き上げられ老いた男の人達も次々と 戦場へ赴きました。その留守を、女子と幼い子供達が守らなくて はなりませんでした。食料は段々と少なくなり、配給制度が行わ れ始め、小さな子供を抱えた人達は大変でした。 山奥の国民学校もその波は打ちよせて、子供達の心にも変化を もたらしていきました。 佐武 昭和二十年の初夏、私にとって忘れられない出来事が・・ ・子供達は食べ物が無く、いっもおなかをすかしている毎日でし た。それでもまだ町のようには非度くはなく、三度に二度は何 かを食べられました。私は、子供達の明るい笑顔ときらきらと輝 く瞳に助けられて、村に割り当てられた供出物確保に山や野原に 出掛けておりました。子供達は、春には蕨や薇や土筆を取り、秋 には松葉を拾いに行き、松の木から松やにを集めておりました。 もう、勉強どころではありませんでした。 長太君は、養成所を終え満蒙開拓青少年義勇軍に入り満州へと 渡りました。どんなに辛い目に合っているか、便りが無いので余 計に案じられました。 明文さんからは、海軍での訓練の様子を時折知らせてくれまし た。 佐武 長太君の件以来、私は教師を辞め故郷に帰りました。そし て、何もかも忘れるために、飛行機製作所へ勤労動員として出ま した。 昭和二十年八月六日、広島に原子爆弾が投下され、八月八日、 ソ連が参戦、十五日終戦。神風が吹くこと無く、日本は多くの尊 い生命を無駄にして破れました。沢山の文化財も灰になりました 。余りにも多くの犠牲でした。そのことで国民は途方にくれ、大 変な混乱が生じました。私の回りにも慌ただしく多くのことが通 り過ぎていきました。私は家に帰りましたが、何をどのようにす れば良いのかわからなく、毎日毎日ぶらぶらしておりました。 幸せなことに、二十一年の春に父は復員して参りましたが、思 い返されることは、辛い悲しい思い出ばかり。お雪ちゃんのお父 さん、健次君のお父さん、校長先生の・・・。そして、私が初め て愛した明文さんの戦死・・・。でも、私の心に重い苦い後悔を もたらすのは、長太君の死なのでした。命の重さは、尊さは同じ かもしれないけれど、私の一言で救えたかも知れない長太君の命 ・・・。教師の言葉、教育の怖さを知る思いがして・・・ 私はこれからどのように長太君に償えば良いのかと、部屋に閉 じ篭もって考え悩んでおりました。が、閉ざした心からは答えな ど、解決策など生まれてくるものではありませんでした。 佐武 昭和二十一年の秋、私は復職いたしました。 蒜山三座は緑から赤へと紅葉し、美しく見えました。人間が愚かな行為によって打ちひしがれているのが嘘のように、自然は泰然自惹として時のうつろいを見せておりました。その姿を見るにつけ、私は自然の美しさ、生命力の強さに負けてはならないと思いました。 子供達はおなかをすかしてはおりましたが、明るく、逞しく立ち 上がろうとしていました。 町では、一枚の干パンを貰うために、毎日毎日、長い行列をつく るとのことでした。それだけではたりなくて、子供達のためにお 母さんは田舎に買い出しに出られ、指輪や着物を米に替え、豆に 、藷にと・・・ だけど、熱心であればあるほど私を信じてくれた子供達にどの ように詫びたらいいのか、僅か二年ではあったけれど、信じて ついて来てくれた子供達にどんな気持ちで接しればいいのか、悩み ました。 それに、今まで使っていた教科書に、進駐軍の指示により墨で 塗り潰すことが私達教師の最初の仕事でした。子供達と私の心に 墨を塗っているようでたまりませんでした。 でも、そんな感傷に浸っている暇はありませんでした。ただ、 今までの過ちをどのように現場に立って償うか、また、これから の教育姿勢をどのようにすればいいか考えました。打ち拉がれ、 何も手に付かないという先生も多く居たようでしたが、私は過去 の事を忘れずにしっかりと心において、その上で子供達の綺麗な 心に接しょうと決めていました。それしか考えが浮かびませんで した。 佐竹は教職に立っていた当時を淡々と語っていたが、目には時折り光るものを帯びていた。 「今日来ていただいたのは・・・「己なき日々」にも書きましたように母と女教師の会の起源といいますか発端と言いますか、その趣旨が曖昧になっておりまして・・・。その演劇を作っていただきたくて・・・このように長々とお話をさせていただきました。母と女教師の会は決して政治的なものではなく・・・ 『教え子をふたたび戦場にやらない』 『教え子を二度と飢えさせない』 『お母さんの体を守ろう』 という趣旨なのです・・・。そのことを若い女教師に知ってほしくて・・・。母と女教師の会で公演をしていただけないかとお願いしたい為で御座います」佐竹はそう言ってほっと一息入れた。 佐竹の言葉は重く省三の背に乗るものだった。そんな活動があったとはぜんぜん知らないことだった。 一人女教師の言葉が発端でそんな大きな運動がなされていたことに驚いた。何かふつふつとわきあがる闘志のようなものが生まれてきていた。 「人間とはなんと素晴らしい」 省三は心の中で叫んでいた。 「私でよろしければやらせていただきます」 省三は震えながら強く言っていた。そばで心配そうに育子が見ていた。 「ありがとう御座います。これで肩の荷が下りました。母と女教師の会が政治運動のようになっておりまして、そのことを危惧して「己なき日々」をその当時の先生方と出したのですが、中々思うようには行かなくて・・・読んでいただけなくて・・・。見てくだされば分りやすくみんなの心の中に入りましょうし・・・」 佐竹は退職婦人教職員全国連絡協議会の副会長の役職にあって、全国をまわっている忙しい体だった。定年を切り上げて幅広い運動を行っていた。 「大変な事になったわね」 育子は心配そうに言った。 帰りの車を運転しながら、 「何とかなるよ」 と省三は明るく言った。頭の中にはストーリーが組み立てられていたのだった。 省三は戦中戦後の物語はたくさん読んでいた。文芸同人誌「怠け者」を各所に送ると必ずと言っていいほど同人誌を贈ってくれた。その中には必ず戦争物が二三作載っていたのだった。書斎の戦争文学も紐解かなくてはと思った。戸倉のところへ行かないときは資料を読み漁った。梅木女史の戦中戦後の童話が特に役に立った。佐竹の話を聞いている間に台本の筋書きはどんどんと組み立てられていたが、その肉付けにはやはり資料が必要だった。段々と頭の中に物語が広がっていった。 一人ひとりの箱書きが始まった。歴史年表が机の前に張られた。大まかに史実が書き込まれていった。 教師自身が最高の教育環境、と言う貫通行動が出来上がった。反感通行動として、息子を取られた母の哀しみ、校長の一億玉砕の精神、愛国心、進駐軍が持ってきた民主主義、母と女教師の会の発足、中国在留日本人を貫通行動にかにませる事にした。書き始めていくらかの変更はあるにしてもこのように書こうと決めたのだった。これが出来ると出来たも同然だった。この作業は一週間ほどで出来上がった。あとは書き始めればよかった。 「子供を十五人ほど集めて欲しいのだけど・・・」 省三は練習の日に戸倉に言った。 「ほほ、やる気になったのか」 戸倉はあっさりと交わした。 「十一月に一つ公演したいんだ。その為に子供が必要なんだ」 「何年生が欲しいのだ」 「六年生を五名、後は何年生でもいいんだ」 「本は・・・」 「これから書く・・・」 「大丈夫か・・・育子さんに叱られないかな・・・」 「迷惑はかけないよ」 「それでどのような物語だ」 省三は佐竹との話を掻い摘んで話した。 戸倉の目の色が変わった。 「秋だな、十一月でいいのだな・・・市民会館をとるぞ」 省三は青年が子供に扮してと考えたが、観客動員を考えれば子供を遣ったほうがいいと思った。 「忙しくなるぞ」 戸倉は省三を引っ張り出したのは今日を予期していたのだった。 「台本は何時上がる」 「五月いっぱいはかかるな」 「夏休みに子供たちをあげられるな」 「段取りを頼むよ」 「わかった」 戸倉はなにやら書き込みながら省三と話した。 「母と女教師の会か・・・教え子をふたたび戦場にやりません・・・教え子を二度と飢えさせない・・・お母さんの体を守ります・・・か・・・これはいいよ、これは・・・。子ども会、婦人会、老人会、PTA、ボーイスカウト、ガールスカウト、海洋少年団、退婦教、教員組合・・・市民会館が一杯になるぞ、これは・・・」 戸倉は狂喜してはや獲らぬ狸の皮算用を始めていた。 省三はこの何週間かは不安発作がない事に気がついた。何かに夢中になれば忘れられるものらしいことを知った。 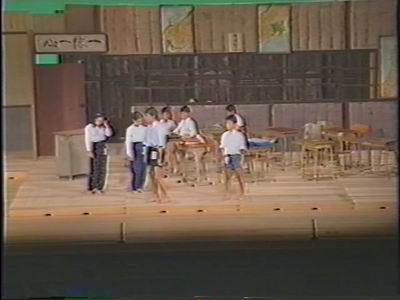 3 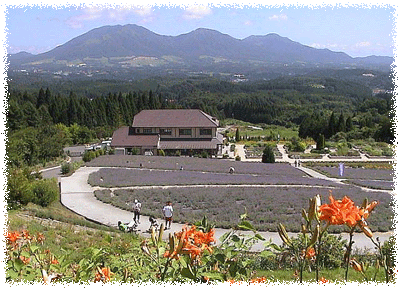 陽炎の中、省三は育子を助手席に乗せ佐竹が勤めていたという分教場を探して走った。 蒜山三座の山並みが新緑に燃えきらきらと輝いて見えていた。窓を開け放って心地よい風を受けながら田地を通り過ぎ木立の林の中を土煙を上げて疾風した。空には白い綿雲が長閑にゆったりと泳いでいた。 「こうして県北に来たのはずーと前に講演できたとき以来ね」 育子は目を輝かせて風景を眺めながら少し弾んだ声を上げた。 「ああ、そんなこともあった」 省三は周囲を見る余裕はなかった。不安発作が何時出るかを心配していた。 「何るようになるわ、命までは取りはしないから・・・。私もあなたも一度は死んだ命なのだもの」と出かける前に育子は省三を励ましていたのだった。 「空気がこんなに美味しかったとは・・・」 「水島に住んでいたら外は何処でも美味いさ」 省三と育子は他愛無い会話の中に幸せを感じ取っていた。 草茫々の中に分教場は埋まるようにあった。運動場の中に錆だらけの鉄棒がぽっんと立っていた。木々の侵食は運動場を侵し空間を狭めていた。校舎の板壁は木の命を終わり朽ちて崩れかかっていた。 省三は鍵のかかった門の前で見詰めた。鍵はかかっているが何処からでも入れた。北側に長い廊下があり、運動場の南に面して教員室に三教室があった。教員室には教科書や書籍が散乱し、薬缶と湯呑茶碗が散らばっていた。教室は机と椅子が黒板の前に一塊で積まれていた。 省三はしばらくそこに立っていた。 舞台明かりが点く。 山の音、例えば鳥の鳴き声とか小川の細流、風が木 立ちを鳴らす音など。 長太が息を切らせて登場する。 長太 あれ、みんなまだ来とらんな。どうしたんじゃろう。 花江が、唱歌「赤トンボ」を口ずさみながら登場す る。長太を見て走りより、 花江 わぁ!長太ちゃん、今日は何かあったん。 長太 お花、なんじゃ。 花江 時計が狂うとったんか、長太ちゃんの頭が狂うとんかどっ ちなん。 長太 やかましい・・・ 花江 お天とう様が西から昇かも知れんで。 長太 なんじゃ、その言い草は・・・せいよりみんなどうしたん なら。 花江 いつも遅れてくるもんがはように来るけえ・・ 長太 そうか、みんなの時計が狂うとんじのう。 花江 そりゃ、長太ちゃんの方じぁが・・・。先生が来られるま でにはまだ時間があるもん。 長太 そうか、わしがはょう来過ぎたんか? 花江 その通りじゃ。・・・今日はどうしたん。 長太 うん、うむ、・・・{考えこんだ} 花江 何かあったんと違う。 長太 いいや、いや・・・何にもありゃせんで、何んにも・・・ 花江 ほんとのほんと。 長太 ほんとじゃ。 花江 ほんと。ほんとのほんとのほんとなん。 長太 ひつけえの。 花江 隠さんでもええが。 長太 ・・・それより、悪かったの。 花江 なんしてなん。 長太 お花はお父と約束したんじゅゃろう。戦争に行くときに、 お花の頭を撫でながら、誰にも負けんように勉強せえ。誰にも負 けんように一番に学校へ行けと言うとるのを、わしはきいとるけ え。 花江 ううん・・・じゃけえどええんよ。 長太 わし、お花が来とるもんと思うて。 花江 ええんじゃ。うちは嬉しいんじゃ。長太ちゃんがこんなに はょう学校に出て来られたんじゃもん。家は忙しいんじゃろう。 長太 そりぁ、お父もあんちゃんも戦争にいっとるけえ。家には おばぁと、おかぁと、妹。男手はわし一人じぁけえ、頼りにされ とるけえ。田の草を取ったり、堆肥をこせいたりせんとおえんけ え。 花江 わぁ!{大きな声ではしゃいだ} 長太 どうしたんなら、びっくりするじゃねえか。 花江 だって、おかしいもん。そんなに力があるようには見えん もん。 長太 このおてんばお花が・・・・。わし、大きゅうなったら兵 隊さんに成るんじゃ。おとんやあんちゃんがたたこうとる戦場に 行くんじゃ。せいで、日本を勝すんじゃ。こんなこたぁおなごに は分からんじゃろう。分かってたまるか。 花江 なんを急に大人のようなことを言うて・・・。じゃあ言う て、うちらが大きゅうなるまで戦争がつづいとるじゃろうか? 長太 この馬鹿、負けるちゅうんか、神国日本が負けてたまるか 花江 そうは言うてねえ、けど、うち心配なんじゃ。兵隊さんに 食べて貰う言うて、蕨や薇や稗を取って・・・。それを食べとる んじゃもん、それでほんとに勝てるん。 長太 女子はめめしゅうておえんけえ。 花江 じゃ言うても・・・。 長太 {直立し,敬礼して}兵隊さんはお国のためにたたこうて おられる。我々は銃後を守る小国民として・・・。 花江 わぁ、まるで校長先生のようじゃ。 長太 ・・・おとうは満州じゃ。あんちゃんはビルマ・・・元気 じゃろうか・・・。 花江 {明るく}大丈夫じゃ。長太ちゃんのおとうやあんちゃん には、鉄砲の弾も逃げよるわな。 長太 お花のおとうは・・・。 花江 うちのおっとうは、中国(シナ)じゃ。こん前の手紙には な、中国人で一杯じゃと書いて来とった。 長太 当たり前じゃ、中国なんじゃけえ。 花江 ああそうか、そうなんじゃなあ。 長太 お花は呑気でええのう。 花江 本当に何かあったんと違う。いっもの長太ちゃんじゃねえ みたい。 長太 なにもありゃせんが・・・。このおっちょこちょいの先走 り屋。 花江 何もそげん言わんでもええが・・・。 長太 みんなそう言うとるぞ。 花江 そげん事言うのぁ誰なん、一人づつやっつけてやるけえ。 長太 おてんばじゃのう、誰ぇも嫁にももろうてくれんぞ。 花江 うちええもん。長太ちゃんのお嫁さんにはならんもん。 長太 わしもおしゃべりは好かんけえ。 健次、お雪が登場する。 お雪 健ちゃん、そんなに走らんで待って。 健次 はようけえ。 お雪 まだ小使いさんが鐘を鳴らすのには時間があるもん。 健次 このぐずのお雪が。 お雪 言うたな。 健次とお雪がじゃれあっている。 長太 こら!おまえら、何んをやっとんなら、銃後を守る小国民 がそんな心構えでええんか。 お雪 {うつ向いた}・・・・・ 健次 どうしたんなら。 長太 どうしたもこうしたんもあるもんか。この非常時に男とお なごが・・・。 健次 せいでも、石井先生は男と女は仲ようせい言われとったけ え。 お雪 そうじゃ、そう言われとったもん。 長太 この馬鹿!石井先生は力を合わせてと言われたんじゃ。 花江 その通りじゃ、長太ちゃんの言う通りじゃ。 健次 チェ! 長太 この非常時になっとらん。 花江 {長太を見て心配そうに}長太ちゃん! 長太 健次、おめいのおとうは海軍じゃったの. 健次 おう、伊号八潜水艦に乗ってドイツにいっといたけえど、 今はインド洋じゃ。 長太 お雪、おめえのお父は・・・。 お雪 {泣きだしそうにして}うちの・・・海軍じゃ今、南太平 洋でたたこうとると・・・。 長太 そんなら、ぼけっとしておられんじゃろうが。 健次 そりゃああ・・・ 花江、長太の表情をじっと見つめている。 長太 {思いを振り払うように}突撃用意!つつ込め撃て!撃て !{教室を走り回って叫ぶ} 健次つられて。 健次 {潜望鏡を覗く真似をして}敵巡洋艦前方四千、魚雷発射 用意!撃て!撃て! 花江とお雪は二人を眺めている。 「あなた・・・」 育子は教室の入り口に立って声を掛けた。育子の声で省三は我に返った。 子供たちが教室にいたのだった。その光景を目のあたりにしたのだと言いたかった。 「車で少し休んだら」 「子供たちが・・・」 「疲れたのよ、あんなに長く運転したの久しぶりなんですもの」 省三は育子に支えられながら車まで歩き、少し横になった。 省三の頭の中には次々と子供たちが出てきて走り回り喜声を上げていた。 ―私に書けというのか・・・この様を綴れと言うのかー 省三は記憶にとどめようと懸命だった。 少し休んで省三はカメラのシャツターを切りまくった。  「順調に上がってる」 戸倉は練習室の机に向って書き物をしている省三に近寄ってきてそう問った。 「ええ、なるべく早く書き上げますから」 省三は笑顔で応えた。 蒜山高原の分教場から帰ってすぐ箱書きに色々と書き足していた。貫通行動に付け加えていた。頭の中ではどんどんとドラマが進行し開幕の台詞と幕締めの台詞が決まっていた。この二つの台詞が決まると殆ど出来上がったと言っていいのだった。映した写真は現像し、洗濯干し場のようにロープを引っ張ったところに洗濯ばさみで留めて吊るした。「己なき日々」は読んでいた。多くの女教師が様々な思いで戦中戦後の教育現場の事情を書き表していた。その行間を務めて読み込もうとした。書けなかったことを読み取ろうと思ったからだった。 省三の脳裏には白いブラウスとモンペをつけ三つ組みに髪を整えた佐竹の姿が動き回っていた。 「教え子の命一つ守れなくてどうして教師だと胸を張って言えるの」 旅館の一室で佐竹は冷静に言い切っていたのだった。 「行かないでと一言言えたら・・・谷本君は行かなかったのです・・・。その言葉がいえなかったばっかりに谷本君は満蒙開拓青少年義勇軍へ行ったのです・・・。そこで亡くなったのです・・・。私が殺したも同然なのです・・・。先生行くなと言ってくれ、そうすりあ行きゃせん・・・谷本君のその声が言葉が私の心に耳に残っているのです」 そう言う佐竹は泣いてはいなかった。むしろ嘲笑しているようだったのだ。 「私はその時に泣くまいと誓ったのです」 この人はそのように生きたのだとその時省三は思ったのだった。並々ならぬ気魄が漂っていた。 「何も知らない女教師に何も教えてくれなかったことを恨んではいません・・・。そのことを感じ取らなかった私にその責任があると感じだのです・・・。その為には巨視が子供たちの手本となり、最高の教育環境にならなくてはと考えるようになりました・・・。子供たちの為なら政治に利用されてもいいと割り切ったのです・・・」 佐竹は今の現状を言った。今は政治運動の一環になっていることを危惧していた。 省三の中で様々な佐竹が動き回り話掛け叫んでいた。それを省三はメモにして確認するのだった。子供たちと遊ぶ佐竹、教壇に立つ佐竹、一人思いにふける佐竹、その時佐竹は何をどのように考え行動したのかを思い巡らせたのだった。長閑で雲が泳ぐ蒜山の麓の分教場であったことをどのように書き表せば佐竹の思いを伝えることが出来るのかに思いをめぐらせた。 佐竹は奇遇だが省三が通った小学校に分教場から転任して来ていたのだった。 そんな先生に担任してもらっていたら少しは真面目に勉強で来ていたか、省三は六年間先生に恵まれなかったのだった。勉強の出来る子と金持ちの子を贔屓する先生ばかりだったのだ。 「先生という立場は一人ひとりの子の人生を変えてしまうことが多いいのです」 佐竹はそこで詰まったのだった。 「日本はその後、愚かな戦争はしなかったけれど・・・世界を見ればたくさんの子供たちが・・・。こんなことを言っては自分を持ち上げているようで恥ずかしいのですけれど、私の年金は総てを開発途上国の教育費に使っていただいています・・・、教材に校舎の建設に・・・人が人の苦しみを見て何もしないという社会は間違っていると思って・・・」 佐竹は着古した紺のスーツを着込んでいたのだった。 それは一人の教え子を救えなかった悔いゆえの行動であったのだ。 省三はその時体を硬くして聞いていたのだった。病気のことも忘れて書きたいと言う衝動が突き上げていたのだ。 「先生、チョツトいいですか」 思いの中から突然現実に返され顔を見上げるとそこには芳子が立っていた。 「歯でも痛いの」 省三は笑いながら言った。 「先生、私は歯科衛生士です」 芳子は笑いながら返した。高校時代演劇部に居て中国大会に出た経験があった。今は歯科医院に勤めながら青年活動をしていた。 最近ではみんなと馴れて冗談も言い合うことが出来るようになっていた。 「なにでしょう」 「今でなくてもいいのですけれど、一度相談に乗ってくださらないかと思って・・・」 「いいですよ、今でも」 「みんなが居ないほうがいいんですけれど・・・」 「そうか、遅くなったら佳世ちゃんに悪いしな・・・」 「タクシー代は私が出しますから・・・」 「その手があったか・・・」 「はい」 「今日は何時もの通り変えると言ってあるから、次ではどうかな」 「ありがとう御座います」 「ところで今書いている台本が上がったら清書して欲しいんだが・・・」 「はい、喜んで」 芳子はきっぱりと言った。みんなの書き物を見て芳子が一番字が綺麗であったので頼んだ。ガリを切るか青焼きをして百冊近く台本は必要だった。省三の字ではみんなが読めないだろうという思いだった。 省三は書きたい心をじっと押さえて頭の中で醗酵するのを待っていた。 醗酵すると言うことは九十九パーセントその作品が完成したと言うことだった。後の一パーセントはただ書き上げればいいと言うことだった。それは省三が作品を書くときに生まれた方法だった。いまだ醗酵しないものを喉から引っ張り出して書くと途中で投げ出さなくてはならなくなることが多いことが分っていた。一日中考えるのではなく、生活の中で醗酵は進むものだった。醗酵は書く切っ掛けなのかもしれなかった。 少し開かれた窓からは五月の緑の風が流れ込んみ、熱がりの省三の額や頬を撫でていた。 小さな足音が近づいていた。 「おとん・・・ご飯」 下の子の豊太が兄の悠一の真似をして言った。 「ありがとう」 省三は豊太を抱いてゆっくりと階段を下りた。 「今日はカツか・・・」 「夜食にサンドイッチを作って置きましたから」 育子はさりげなく言ったのだった。 「おとん、食べよ」 悠一が催促をした。 省三はこの幸せを奪う奴を許すものかと思った。 「これくらいで間に合うかしら・・・」 育子はニダスーの鉛筆を削って出したのだった。 ―書け、今日から書けというのか、育子には私の心の中にあるものが醗酵したのが分るのかー 省三は小説を書くときは万年筆を使い、戯曲のときは鉛筆を使っていた。戯曲はなるべく喋る速さで書くことを望んだからだ。その為には万年筆より鉛筆の方が良かった。 食事を早々に済ませ、二人の子供たちを風呂に入れ書斎に篭もった。机の前に垂れ下がる蒜山一帯の写真を眺め、箱書きを読み、貫通行動と反感通行動が幾重にも交差する図式をじっくり読み込んで確認した。原稿用紙も記名入りの少し厚めのものを用意した。 降臨というのか、自然に手が文字を紡いでいた。室内にはモーツァルトの音楽が流れていた。 省三は朝までに百五十枚を一気に書き上げた。 体には何の変化もなく順調だった。窓には朝の光が差し込んでいた。眩しかった。 「ご苦労様」 育子が見ていたように熱いコーヒーを運んできた。 「書き上げたよ、これを添削して清書をしてもらうよ」 省三はコーヒーの香を鼻にし口に運んだ。緊張感が緩み快い疲労感を感じていた。 4 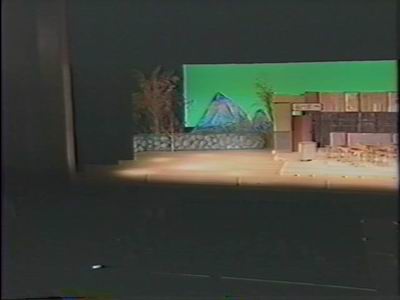 「少し問題があるね・・・君の家庭の事情を知っていて・・・」 省三は少しくぐもった声で言った。芳子の家庭は父親が早く亡くなってははと弟の家庭だった。 「私のことを・・・」 「何もかも捨てて来いとは・・・」 相手の男はピァレントの助手をしている人で、一人旅で泊ったときに知合ったのだと言った。 「私どうしていいか分らず・・・」 「好きなのですか」 「はい・・・でもこの手紙を読んでからは・・・心が分からなくなって・・・」 「お母さんには・・・」 「言ってません」 「少し時間を置いて・・・」 芳子との話は平行線だった。芳子は泣くだけだった。 省三は家まで送った。 「ゆっくりでいいから清書、頼むね」 芳子は頷いて小走りに家の中へ消えた。 次の練習日に芳子は清書をした原稿を胸に抱きながら入ってきた。この前の話が嘘のように溌剌としていた。 「はい、出来ました。先生に貸しが出来ましたね」 芳子は笑って言った。 「ありがとう、何かでお返しをするよ」 「出来上がったんだって・・・どれどれ・・・」 戸倉が目を輝かせながら近寄ってきた。 「はい、芳子君に清書をしてもらったから読めると思いますよ」 「読まなくてもいい、直ぐに本にして配らなくては・・・」 戸倉は一世一代の出し物に狂喜していた。 「中々評判はいいよ・・・話だけで乗ってくる人も多いいから・・・その人たちに台本だけでも配り繋ぎ留めておかなくては・・・」 戸倉はいそいそと印刷の準備に取り掛かった。 「私は石井がいいな・・・やりたいわ」 芳子が言った。 「私には配役の権限はないから・・・」 「先生が反対をしなかったらいいの」 「反対はしないさ・・・やる気のある人がやればいいと思っているから・・・」 「やる気なら誰にも負けないは・・・」 大人が十八人、子供が十五人いる台本だった。五人ダブルキャストでやれた。 六月の初めキャストとスタッフが決まり練習が始まった。 健次 おい、そこの疎開もん、魚雷の用意じゃ。 春子ポカンとしている。 長太 {花江とお雪に}そこの二人、何をぼけっとしとるんなら 。突っ込め、撃て撃て撃って撃って撃ちまくれ。 花江 うちは好かんけえ。 長太 何を、この非国民が。 花江 うちは非国民とは違うけえ。 お雪 止めて!{大きく叫んだ} 健次 わあぁい、魚雷敵艦に見事命中!黒い煙を上げとるぞ。あ あ、火を吹き出したぞ。傾いたぞ。やったやった、わあぁい{何 度も何度も飛び上がった} 長太 海軍に負けるな。前進前進、突っ込め。倒れたらおえんぞ 。撃て、撃て、敵の陣地を占領しろ 長太と健次は走り回っている。そこえ生徒達が登校 してくる。それぞれに別れて、叫びながら駆け回っ ている。数がだんだん増える。 お雪 {大きく}止めて!止めて!{泣きだす} 健次 なんを、この泣き虫お雪が。 お雪 健ちゃんのバカ、バカ・・・ 花江 {長太の前に立ちはだかり}やめられえ!ちいたぁ、お雪 ちゃんの身にもなったげられえ。 長太 なにを・・・どうしたんなら。 花江 {長太を睨み付けている} 長太 だまっとったらわからんがな・・・。 健次や他の生徒ははしゃぎ回っている。 花江 この、薄らトンカチの分からず屋。 長太 {お雪を見て}・・・健次、やめい。他の者もやめい。 健次 {不服そうに}うん。 他の生徒もそれにならって止める。 長太 お雪がどうかしたんか。 お雪 うちは、嫌いじゃ、好かんけえ・ 健次 {お雪に近ずいて}なんかあったんか? 花江 お雪ちゃんはなあ・・・。 お雪、運動場に走りでる。春子が後を追う。 健次は心配そうに窓から覗いている。 花江 この三か月ほど、お父から便りがないらしいんじゃ。 長太 そうか、そうじゃつたんか。 木の下で泣いているお雪に、長太教室より出て行っ て近寄り。 長太 わしゃ、わしゃ・・・・悪かったの。 お雪 {かぶりを振る} 春子 早く、教室に入ろう。 長太 そうじゃ、もおせんけえ。 お雪は春子に押されながら教室に入る。長太は頭を 掻きながら入ってくる。 花江 長太ちゃん、お雪ちゃんに謝られい。 お雪 うち、うち、もうええんよ。 花江 お雪ちゃん、きっと、お父から手紙がくるけえ。 お雪 うん、そうじゃろうか。 長太 そうじゃとも。分の厚い手紙がもう届く頃じゃ・・・何せ 、郵便配達のおっさん腰が曲がってよおよお自転車にのっとんじ ゃけえ。 健次 あのおっさんもだいぶくたびれとるけえなぁ。 花江 そうじゃ、学校から帰ったら、お雪元気かって書いた手紙 が来とるって。 お雪 そうじゃろうか。 長太 そうじゃ、そうにきまっとるけえ。 花江 {ぼさーとしている健次に}そうよね、健ちゃん。 健次 {ハッとして}う、うん、おらもそう思うで。 お雪 そうじゃね{笑った} 健次 今、泣いとったカラスがもう笑うとんじゃけいな。 お雪 もう、うちしらん。 子供たちは練習所を走り回っていた。戸倉がカブスカウトの子供たちを集めてきていた。 省三はこれから始まる舞台のことを考えたら心が浮き立つものを覚えていた。 これで「春の路」を終えさせていただきます。 読んでくださいましてありがとう御座いました。Yuu yuu 2006/02/08 脱稿 この小説は 海の華の続編である 冬の華の続編である 春の華の続編である 夏の華の続編である 秋の華の続編である 冬の路の続編である 春の路の続編である彷徨する省三の青春譚である。 秋の路へ続く ご興味が御座いましたら華シリーズもお読み頂けましたら嬉しゅう御座います。 ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
|